これらの本は、Googleで「南インド料理」と検索すると見つけられる書籍です。
全ての書籍を購入し、気に入った料理を作ってみたりもしました。
もし南インド料理を作ってみたいと思う方にはおすすめの書籍です。
作ろう!南インドの定食ミールス
まずは沼尻さんのミールスの作り方を玉置さんが書籍化したものですが、私が初めて食したミールスは沼尻さんの作るミールスでした。最初は沼尻さんの作るミールスを食べる会のような催しに何度も足繁く通い、どのように調理をするのか、じーっと観察していたことが思い出されます。
当時のデータを記録していたmixiにログインすることができなくなってしまいましたが、この書籍に目を通すたび、御徒町の改札前で待ち合わせをし、アメ横の大津屋さんでスパイス、八百屋さんや吉池で野菜を購入し、上野松坂屋前から都バスに乗って新宿榎町の地域センターまで移動して食事会に参加したりしていた時のことを思い出します。時間内に調理を完成し、食事を済ませ、片付けまで完了しなければなりません。ちょっと緊張感の漂う?雰囲気の中、習うより慣れろ的な雰囲気のあった食事会、だったと今は思います。沼尻さんの作るミールスの手順を事細かくわかりやすく記載されていますので、「目から鱗」的なレシピ本であると思います。一家に一冊。なければ電子書籍でも。
家庭で作れる南インドのカレーとスパイス料理
続きましては、キッチンスタジオペイズリーの香取先生の南インド料理レシピ本です。
再現性を重視し、調理手順にこだわったレシピ本。仮に『え?』と思うような分量を使用するものがあったとしても、そのままの分量で調理して欲しい。と香取先生は以前おっしゃっていました。
汁物、炒め物、ベジ・ノンベジ共に、美味しい南インド料理が作れると思います。
ちなみに、赤穂の天塩がレシピ作成時に使用されたお塩です。お好みのお塩がなければ、赤穂の天塩で作ってみてください。
新版 誰も知らないインド料理
書店で「ごちそうはバナナの葉の上に」と一緒に購入した「誰も知らないインド料理」。この本を読むまでは、インド料理のこと、知りませんでした。当時の私はタンドリーチキン、バターチキン、ナンばかり食べ、そして胃もたれ・・・。インドカレーってそういうものだとばかり正直言って思っていました。菜食?どんなの?そんな私がキャベツのポリヤルを作るために、日比谷線の仲御徒町で下車し、アメ横の大津屋さんで必要と思われるスパイスを購入しました。
上野駅から京浜東北線に乗車し、帰宅。最寄駅の近くにある八百屋さんで玉ねぎやキャベツを購入し、たくさんのポリヤルを作りました。
書籍自体は、写真も少ないけれど、レシピは丁寧に書かれていて、想像力を掻き立てられる書籍です。
その「誰も知らないインド料理」ですが、いつの間にか絶版になってしまったようです。しかし、出版社が代わり12年ほど前に復刊され「新版 誰も知らないインド料理」として生まれ変わりました。
相変わらず写真は少ないのですが、文庫本サイズとなり、使い勝手はよくなったかと思います。
南インド料理以上に他のエリアの料理も充実していますので、他エリアの料理も美味しく作れるかと思います。
10数年前は、材料を全て揃えることは難しかった(フレッシュなカレーリーフはなかなか入手困難で乾燥したカレーリーフを代わりに使用したりしていました)のですが、今はフレッシュなカレーリーフも入手しやすくなりましたのでさらに美味しく掲載された料理を作ることができるかと思います。
カレーな薬膳
「サザンスパイス」という教室を主催されていた渡辺 玲先生のレシピ本。この書籍の前に「誰も知らないインド料理」と「ごちそうはバナナの葉の上に」が発刊されていましたが、「ごちそうはバナナの葉の上に」は絶版となってしまいました。日本に南インド、南インド料理を紹介する書籍がほとんどない時代に出版された書籍(インドを食べる: 豊穣の国・啓示の国 著者:浅野 哲哉はありましたが)。南インド料理のバイブル的な書籍でした。その4年後に出版された「カレーな薬膳」。通勤中の電車の中で読んでは、帰宅後の自宅で何度もレシピを参考に料理してました。懐かしいです。もう21年も前に出版された書籍ではありますが、スパイスの効果効能を元にこういう時にはこういう料理を食べると効果があると書かれており、ご自身の経験をふまえて教えてくれます。漢方薬も基本はインドでも使用されるスパイスです(一部ないものもありますが)から、カレーを食べて健康になれる。購入できる方は、ぜひ読んで欲しい書籍だと思います。
南インド料理店総料理長が教える だいたい15分! 本格インドカレー
本書を読んでの感想は、「すごい!」その一言に尽きます。
本書を購入し、目次に目を通しました。キャッチーな料理も多くありますが、基本的なことも多く書かれています。
以前、10分でできる南インド料理という書籍がありましたが(この書籍の料理もかつて何度も作ったものがあります)、10分では到底作れない料理も多々ありました。(笑)
本格的といわれる料理でも稲田さんのアレンジによって、多くの人が美味しいと感じる料理が本当に「だいたい15分!」あれば作れてしまうようです。
欲を言えば、伝統的な(時間のかかる)調理法とアレンジされた調理法の2種類を併せて記載してもらえたら、個人的にもものすごく勉強になったのではとは思ってしまいましたが、人気のある料理が短時間で簡単に作れるのですから、やはり、稲田さんはすごいなぁ、と感じましたし、このテーマも素晴らしいと思いました。
稲田さんのテクニック満載の本ですから、まずはレシピ通りに作って、その極意ごと味わって楽しんで欲しいレシピ本だと思いました。
南インド料理とミールス
著者は銀座の老舗インド料理店「ナイルレストラン」の3代目 ナイル善己さん
この本の出版記念イベント、夫婦揃ってお伺いしました(笑)懐かしいなぁ 今でも当時いただいた木ベラは大切に使用しています。
この本、待ち望んでいた方多かったと思います。
料理も前面に打ち出したミールスだけではなくベジ(菜食料理)、ノンべジ(非菜食料理)、ビリヤニ、スイーツと多くの内容に加え写真も多く掲載されています。南インド料理で使用するスパイスも
私の周りにも、この書籍や香取薫さんの書籍を購入し、南インド料理に目覚めた人も多いと思います。
南インド料理ってなんだろう?どんな料理があるんだろう?ミールスって??という方だけではなく、ちょっと辛めの酒の肴になるおつまみを覚えてみたいと思っている方、「チキン65」や「マトンペッパーフライ」、「フィッシュフライ」も美味しいですよ
これからどの書籍を購入したらいいかと迷われているのであれば、図書館や書店でご確認ください。
MASALAWALA SOUTH INDIAN COOKBOOK
この書籍については、編集を担当された島田さんがnoteに熱く語っている記事がありました。
『MASALAWALA SOUTH INDIAN COOKBOOK』発売です
阿佐ヶ谷書院の新刊、インド料理ユニットのマサラワーラーによる南インド料理のレシピ本『MASALAWALA SOUTH INDIAN COOKBOOK』が発売となりました。ぼくは編集担当しただけではありますが、ここでは本の紹介と発売経緯などを書き残しておければと。
マサラワーラーは武田尋善さんと鹿島信治さんによる二人組のインド料理ケータリングユニットで、呼ばれれば東京はもちろん日本全国どこへでも行きますし、インドで現地のインド人を相手に料理を振る舞ったりしたこともあります。ごく少数のお客さんから数百人レベルのお客さんまで、幅広く対応もしています。
そんなマサラワーラーの二人とぼくとの付き合いはなんだかんだ10年以上前からあり、2014年には井生明さん、春奈さんとの共著で『南インドカルチャー見聞録』という書籍を書いてもらったりもしています。ちなみにこちらいまでも好評発売中です。南インドを知るうえで、とても役立つ書籍です。あ、それはそれとして、マサラワーラーによる南インド料理のレシピ本はいつかやれたらなと思いつつもなかなかやれなかったりもあったんですが、とうとう去年やろうと思い立ち、二人とどんな本にしようかと打ち合わせ。南インド料理といってもとても幅広く、マサラワーラーが作っているメニューだけでもかなりの数。限られたページ数で何を紹介しようと考えていたとき、ミールスについてはナイル善己さんや沼尻匡彦さんたちがすでにレシピ本を出しているわけで、ミールスのレシピ本をやらなくてもいいかなとも思っていましたし、ティファンについては紙のレシピだけで説明するのが難しいなどもあり、南インドのノンベジの魅力を引き出せるようなものにしようとなりました。
まだまだ続く島田さんのノート。ぜひご覧ください。「阿佐ヶ谷書院さんのnote」
南インドカルチャー見聞録
阿佐ヶ谷書院さんの書籍第一段の書籍「南インドカルチャー見聞録」。南インドのあれやこれや、いろんなことが書いてある書籍です。文化的なことは全くちんぷんかんぷんだった私ですが、一応目をとおしました。(笑)
販売開始からすでに約10年。まだまだ増刷され続けている南インドカルチャー見聞録。
地球の歩き方もいいけれど、カルチャー見聞録はおすすめだと思います。
この書籍についても阿佐ヶ谷書院さんの島田さんがnoteにいろいろと書かれています。私の感想よりそちらを読んでいただいた方が役立ちそうなので、ご覧ください。
阿佐ヶ谷書院をやることになったわけ
2013年、いまからもう8年近く前になりますが、カメラマンでインドのチェンナイにも住んでいたことのある井生明さんと、インド料理ユニットのマサラ―ラーから、南インドに関する書籍を出版したいと相談をされました。彼らとはカレーやインド絡みでその前から知り合いであったし、単純にぼくが南インドについての書籍はあれば読みたいと思っていたし、最初は既存の出版社に南インドについての書籍を出したいと企画の相談をぼくのほうでもしてみましたが、いまほどの南インドの知名度もない2013年には(いまもそこまであるわけではないですが)早すぎたのか、どこも微妙な反応でした。ぼくがひとりで出版社をやってみようと思っていたこともあり・・・ 「阿佐ヶ谷書院さんのnote」南インドカルチャー見聞録発売
2014年10月に阿佐ヶ谷書院の刊行書籍第一弾として、井生明・春奈&マサラワーラーによる『南インドカルチャー見聞録』を発売するわけだけど、当時は「南インド」ということについての認識がまだまだ低いことや(いまも一般的にみればそんな高いわけではないけど)、いきなり阿佐ヶ谷書院という訳のわからない出版社の新刊といわれても書店だって取りづらいわけで、初回の取次への搬入部数はびっくりするぐらい絶望的な部数で・・・ 「阿佐ヶ谷書院さんのnote」

Dakshin Bhog: Flavours of South Indian Cooking


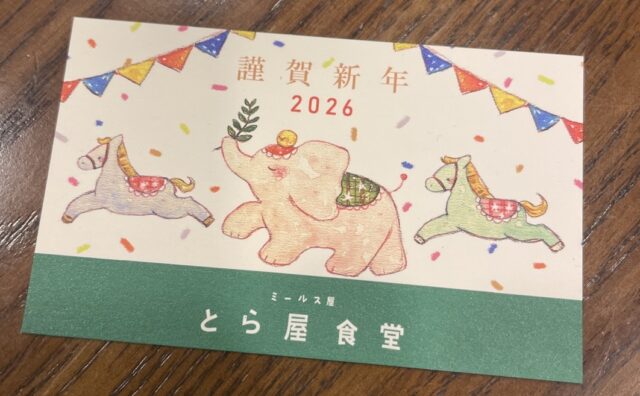





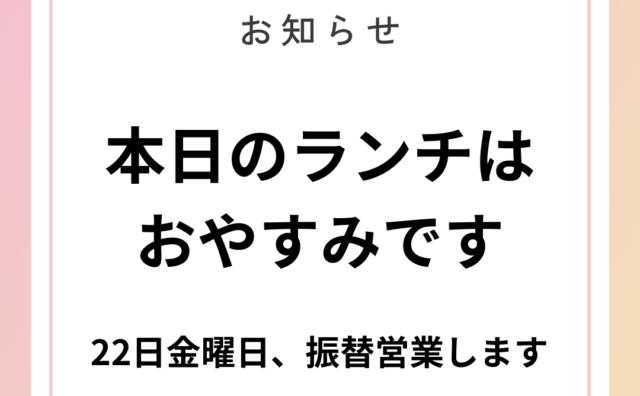








コメント